-
「令和7年度 第2回 学力向上推進研修」が行われました(2026.2.3)
- 公開日
- 2026/02/04
- 更新日
- 2026/02/09
「読む力」の育成
2月3日(火)、令7年度 第2回 学力向上推進研修がありました。
主に各学校の研究主任が参加し、実証研究校と学習指導センターが「読む力」育成の取組について発表し、各中学校区で情報交換を行いました。
次年度の取組の発展が期待される会になりました。
開会のあいさつ
岡村教育長が、学校現場で教育活動に尽力いただいている先生方へ感謝と激励を伝えた後、
「読むことを通して語彙を豊かにすることは、その後の読解や表現の基礎になる」といったお話をしました。
実証研究校の発表
北辰小学校
○メンター制による職員研修体制
○「読む力」育成の視点を入れた授業研修
○「読む力」育成に向けた担任1人1取組
○「よみかきタイム」(北辰版RSノートの試行)
・全校朝会時に取組の目的・意義を説明し共有
・隔週・朝の15分間 視写活動
六日町小学校
○「読む力」育成を目指した授業実践
○「読む力」育成の取組ミニレポート(自学級・毎学期)
・「比べる」「選ぶ」「並び替える」場
・互いの読みを交流する対話活動
・読みを自覚するための振り返り
○司書教諭と連携した読書環境の充実化
六日町中学校
○RSTにおける「読む力」の焦点化
○全校授業研修
○教科別授業研修
○レポートの作成・共有
・「読むこと」を「話すこと」「書くこと」と関連付けて指導
○視写活動(各教科主任と研究推進委員会の連携)
学習指導センターの説明学習指導センター指導主事が、「読む力」育成のこれまでの取組を振り返り、RSTの結果を基に、学校や児童生徒に見られた変容を紹介しました。そして、これまでの取組や研修等から見えてきたことと、今後の取組について説明しました。各中学校区の情報交換「読む力」を育む各学校の取組や、次年度の授業研修、及び研究主任会のもち方について話し合いました。参加者の声
・実証研究校の取組を聞くことができ、大変参考になった。・校内で目指す姿を共有したり、取組について考えたりすることが大切だと感じた。・今後の市の取組について知り、見通しをもつことができた。・中学校区の研究主任同士で情報交換をすることができて有意義な機会になった。・各校の公開授業の指導案が閲覧できると、今後の参考にすることができると思った。 など+1
-
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2026/01/08
- 更新日
- 2026/01/08
お知らせ
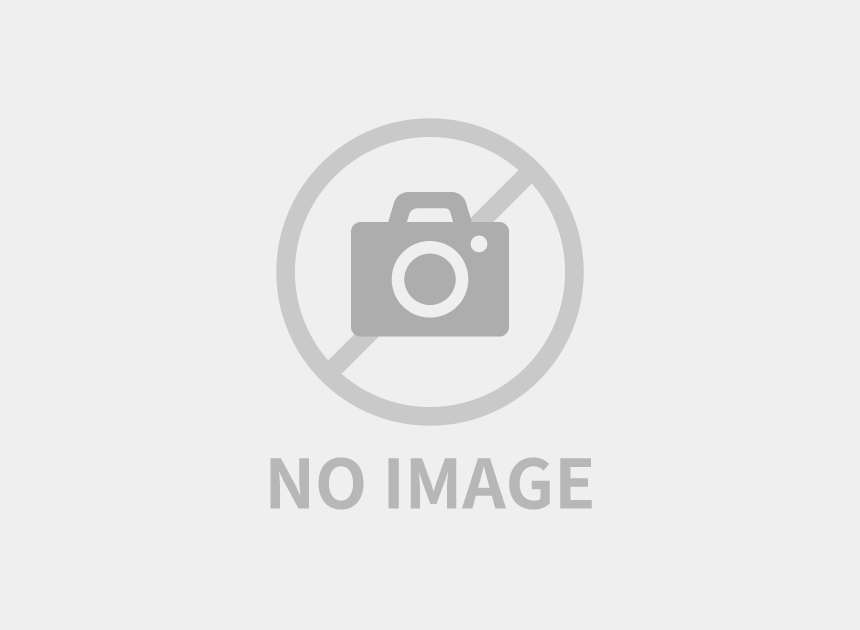
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第9号(令和8年1月号)を掲載しました。
-
「読む力」育成に向けた授業づくり研修(国語)が行われました(2025.11.6)
- 公開日
- 2025/11/21
- 更新日
- 2025/11/21
「読む力」の育成
南魚沼市学習指導センターでは、市内の学校の先生方と共に「読む力」育成のための取り組み方について研修を行っています。11月6日(木)に六日町小学校で、授業づくり研修が行われました。
公開授業
授業は、小学校1年生 国語『いろいろなふね』の学習でした。
本時のねらいは、「フェリーボートの文章を正しい順番にする活動を通して、文章の内容や船の特徴を捉えることができる」でした。
「教材を並び替えて提示する」というしかけにより、「正しい順番に並び替えたい」という気持ちを引き出し、そのために着目すべき言葉や内容を仲間と協力しながら捉え、文章の構成が「やくめ」→「つくり」→「できること」になっていることをに気付くことを目指した授業でした。
「読む力」育成の手立て
授業の様々な場面で、「読む力」を育てるための工夫がなされていました。
1 ダウト読み【正しく読む】
導入では、文章を正しい順番に並び替える際に着目してほしい言葉を意図的に授業者が間違えるダウト読みを行いました。子供たちは、授業者の音読を集中して聞き、間違えに気付くと、大きな声で指摘していました。
2 大事な言葉に線を引く【深く読む】
「フェリーボート」の文章を一斉に音読した後、大事な言葉に線を引くように指示しました。子供たちは、自分で線を引いた箇所を根拠に、自分の考える正しい順番の妥当性を説明していました。
3 比較して読む【深く読む】
前時に学習した「きゃくせん」について書かれた文章を、拡大して教室に掲示しておきました。間違った順番に並んでいる「フェリーボート」の文章と比べ、共通点や相違点に子どもたち自身で気付くことができるようにしました。「きゃくせん」の文章の構成を捉え、それを理由に自分の考えを説明している子がいました。
4 仲間の発言や考えを言い換える【正しく読む】
「鏡会話」というネーミングをつけ、1人の子の発言を、全体やペアでもう一度説明し直したり、共有したりする機会をつくっていました。仲間の発言を何となく聞くのではなく、全員の学びとなるように、聞いたことをアウトプットする機会を意図的に設定していました。
参観者の声
・1年生児童が「ダウト読み」や音読で文章を『正しく読み』、前時の文章構成の掲示などを手掛かりに、大事なところに線を引きながら『深く読む』姿を見させてもらいました。直観から論理への橋渡しのための手立てとした「順番を変えた文章の掲示」によって、文章の型や書かれている内容に注目しながら読んでいく様子が見られ、とても参考になりました。
・説明文教材で「文章構成を学ぶ」という内容が、1年生でもできるのだなという学びがありました。「どう気付かせるか」というところは難しいところではありますが、本時の子供たちの様子は、たくさんの子供たちが直感的に構成を捉えていたように見て取れました。自分でも色々な方法を試し、文章構成をいかにつかませるか、実践を積みたいと思います。
-
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/11/20
- 更新日
- 2025/11/20
お知らせ
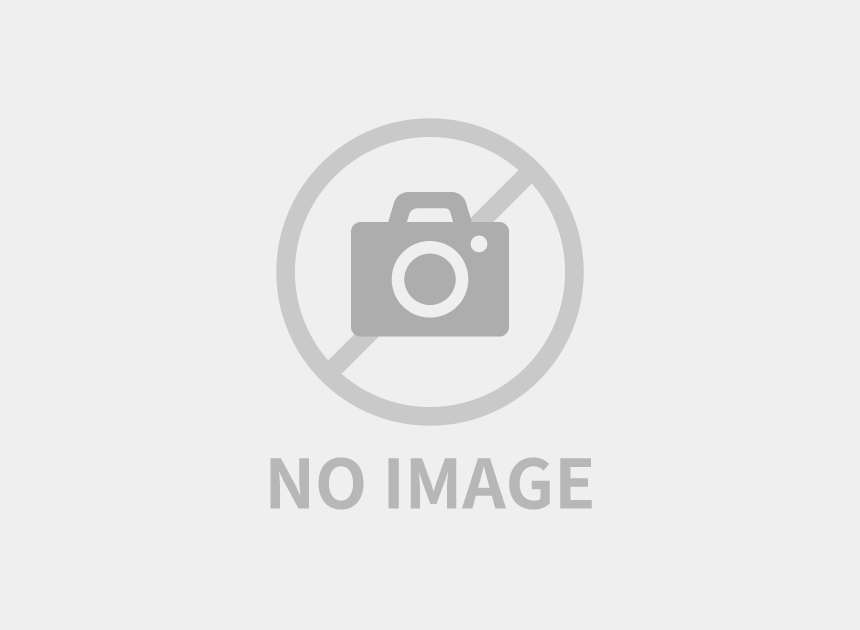
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第8号(令和7年11月号)を掲載しました。
-
「読む力」育成に向けた授業づくり研修(外国語)が行われました(2025.10.2)
- 公開日
- 2025/10/24
- 更新日
- 2025/10/24
「読む力」の育成
南魚沼市学習指導センターでは、市内の学校の先生方と共に「読む力」育成のための取り組み方について研修を行っています。10月2日(木)に北辰小学校で、授業づくり研修が行われました。
公開授業
授業は、小学校3年生国際科 Let’s Try! Unit8 What’s this?の学習でした。
単元のねらいは、「ヒントを出して目の前の物が何であるかを相手に伝え合う活動を通して、そのヒントとなる特徴や様子を表す英語に慣れ親しむ」ことでした。単元の最終授業である本時では、ゲストの先生を迎え、日本のアニメキャラクターについて、その特徴を英語で考え、伝える活動を行いました。 (例)伝えるもの:strawberry ヒント:It’s a fruit. It’s red. It's a triangle.
本時の流れ
◎相手に伝わりやすいヒントを考えよう
1. あいさつ
2.フォニックス
3. Small Talk
4. グループ活動
5. 振り返り
また、授業者は、本時における「読む力」の育成を、正しく「聞く力」と関連づけて捉え、効果的な聞く場面を設定しました。また、授業のさまざまな場面で、「読む力」を育てるための工夫がなされていました。1 目的・状況・場面を捉えるためのSmall Talkの実施グループ活動に入る前に、授業者とALTがSmall Talkを行い、日常生活の中で「ヒントを出して目の前にある物を伝える」場面を実演しました。Small Talkの中には児童にとって難しい表現も含まれていましたが、授業者とALTのリアクションやジェスチャーを交えたやりとりを通して、児童は最終的にその目的・状況・場面を正しく理解することができました。2 理解したことや既習の知識をもとに、自分の考えを作り出す中間指導グループでヒントを作る活動では、自分たちの考えたヒントを英語にすることが難しく、児童の間でさまざまな意見交換が行われていました。そこで授業者は、児童の疑問を全体で共有する「中間指導」の場面を設定しました。児童の一つひとつの「問い」に耳を傾けながら、既習事項の活用や、日本語を英語に直す方法について丁寧に説明しました。特に、日本語の意味が同じ別の文に言い換える「同義文判定」の考え方を伝えることで、「読む力」を育てる支援が行われていました。
その後、児童は再びグループに戻り、先生たちの指導を参考にしながら、相手に伝わるヒントについて再考しました。
最終的に、各グループが考えたヒントを伝え、ゲストに日本のアニメキャラクターを理解してもらうことができました。
本時のキーセンテンスである “What’s this?” を積極的に使いながら、児童は具体的な場面で英語を実際に活用し、学びを深めていました。+2
-
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/10/23
- 更新日
- 2025/10/22
お知らせ
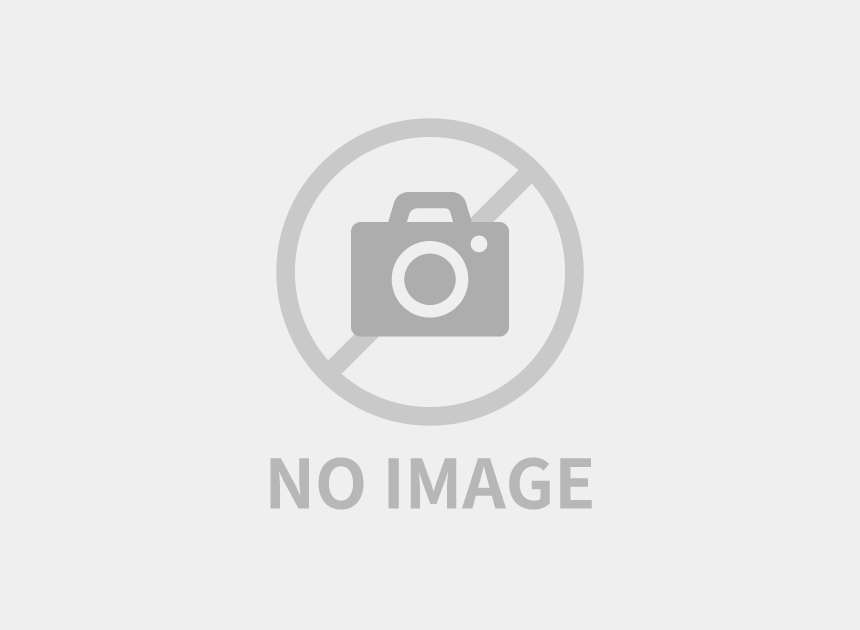
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第7号(令和7年10月号)を掲載しました。
-
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/09/25
- 更新日
- 2025/09/24
お知らせ
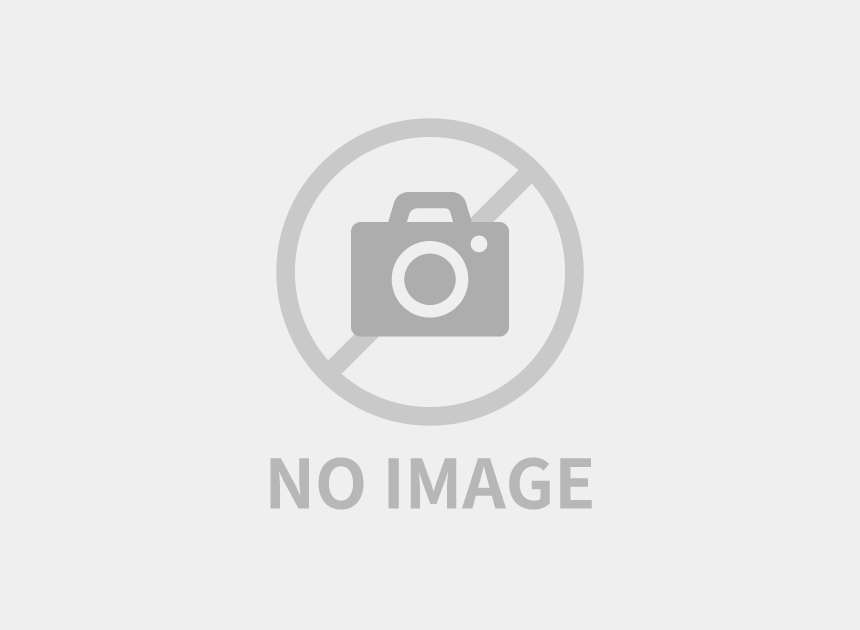
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第6号(令和7年9月号)を掲載しました。
-
情報モラル研修
- 公開日
- 2025/09/19
- 更新日
- 2025/09/19
ICT・情報モラル教育
7月28日(月)センター主催の「情報モラル教育研修」が行われました。今年度は講師に一般財団法人インターネット協会の大久保 真紀様をお招きし「社会で、デジタルウエルビーイングを!」演題に対話形式による研修を実施しました。以下に講演の概要をお伝えします。
近年、インターネットの利用が低年齢化し、長時間の使用も加速しています。このような状況の中で、大人が「使いすぎでは?」と心配して声をかける場面も増えています。しかし、子どもたちが夢中になっていることを頭ごなしに否定するのではなく、対話を重ねることが大切です。
今、求められているのは「デジタルシチズンシップ教育」です。これは、デジタル技術を活用して社会に積極的に関わり、参加できる人を育てる教育です。そのためには、大人自身が情報モラル(適切な行動の考え方や態度)や情報リテラシー(情報を選び活用する力)を理解し、子どもとの継続的な対話を通じて関わっていくことが求められます。
子どもたちが情報を見るのをやめられない背景には、アルゴリズムによって趣味や関心に合った情報が繰り返し表示される仕組みがあります。だからこそ、「本当にそうなのか?」「他の見方はないか?」と疑問を持ち、客観的・論理的に考える力(クリティカルシンキング)を育てることが重要です。
また、インターネットへの投稿が「非日常の楽しみ」として無意識に行われることもあります。こうした状況では、思いやりや配慮が欠けてしまう危険性もあります。他者への意識や客観性を育むために、学校での体験活動を大切にしていきたいところです。
最近では、「親がスマホを自分より大事にしている」と感じる子どもが約2割いるという調査もあります。スマホなどのデジタル機器は、「幸せのため」に使うものであるべきです。大人も子どもも、スマホとの向き合い方を見つめ直しながら、心身ともに健やかにデジタルを活用できる社会(デジタル・ウェルビーイング)の実現を目指していきましょう。
-
令和7年度 市内教員全体研修・教育講演 ~子どもたちのシン読解力を育む授業とは~(2025.8.20)
- 公開日
- 2025/08/22
- 更新日
- 2025/08/25
「読む力」の育成
8月20日(水)、令和7年度 教員全体研修として教育講演が行われました。今年度も一般社団法人「教育のための科学研究所」より、上席研究員の目黒朋子様をお迎えしました。市内の学校より330名程の多くの先生方が参加しました。「シン読解力」とは、教科書を読み解くために必要な読解力のことを指します。
授業内外での指導例を具体的に示していただきました。
「シン読解力」を育む授業(会津美里町立高田小学校の授業より)
◇10分予習
・教科書を読んで気になる部分や大切だと思う部分に線を引いたり、資料と対応する本文の部分を矢印で結んだりする。
※低学年は3分復習・3分予習 (ランドセルに翌日の準備をする時に教科書を見る)
◇掲示物
・グラフの読み取り方 (タイトル、軸の内容と単位、変化、ちがい、など)
・助詞の穴埋め問題 (例.私□、おじいちゃん□てがみ□おくりました。) など
◇ICTの活用
・Google Classroomで教科書の読み方やWebニュースなどを閲覧できるようにする。
・電子黒板で、本時授業の流れや資料を提示する。
◇RSの視点を取り入れた活動
・教科書で根拠を共有する。
・音読して定義を確認する。
・課題を共書きする。 など
◇RSノートの活用
RSノート
・朝の帯時間などを利用して行う。
・教師が意図的に、教科書から既習の教材文を扱い、次のような活動を行う。
①目標設定 (1分間で視写したい文字数の目標を各自が立てる)※目安「学年×10」
②頁を開く (教科書の指定された頁をすばやく開く)
③指さし確認 (指定された文章をすばやく見付ける)
④黙読 (自分は文章が読めるか、どんなことが書かれているかを大まかに捉える)
⑤一斉音読 (皆でことばのまとまりに注意して読んで文意を捉える)
⑥範読 (子供は聞きながら文章や言葉の読み方を確認して文意を捉える)
⑦視写 (1分間視写する)
⑧点検 (隣の人と交換して誤字をチェックする)
⑨評価 (正しく視写した文字数を計算して記録し目標と照らし合わせる)
⑩内容確認 (係り受けや照応などRSの視点からの発問に対し文章を基に答える)
・特に②③④⑤⑦は、授業の課題に関係なく学習に必要な作業であり、これらが自然にできると、課題に集中して取り組むことができるようになる。
・⑩は、教科書を正しく読み、教科の用語に慣れ親しむ上で重要な活動である。
以上のことを実践している小学校の実際の授業や児童の日常会話は、私たちにとってよい刺激となりました。この研修を踏まえ、各学校と共に「読む力」育成に向けた取組を継続するとともに、その質を上げていきましょう。
-
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/08/22
- 更新日
- 2025/08/21
お知らせ
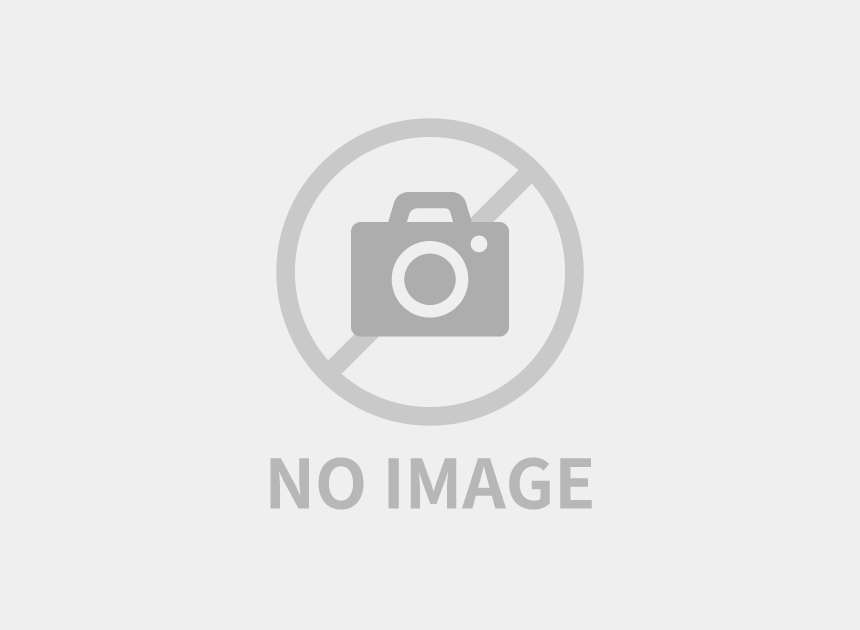 配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第5号(令和7年8月号)を掲載しました。
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第5号(令和7年8月号)を掲載しました。 -
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/07/17
- 更新日
- 2025/07/17
お知らせ
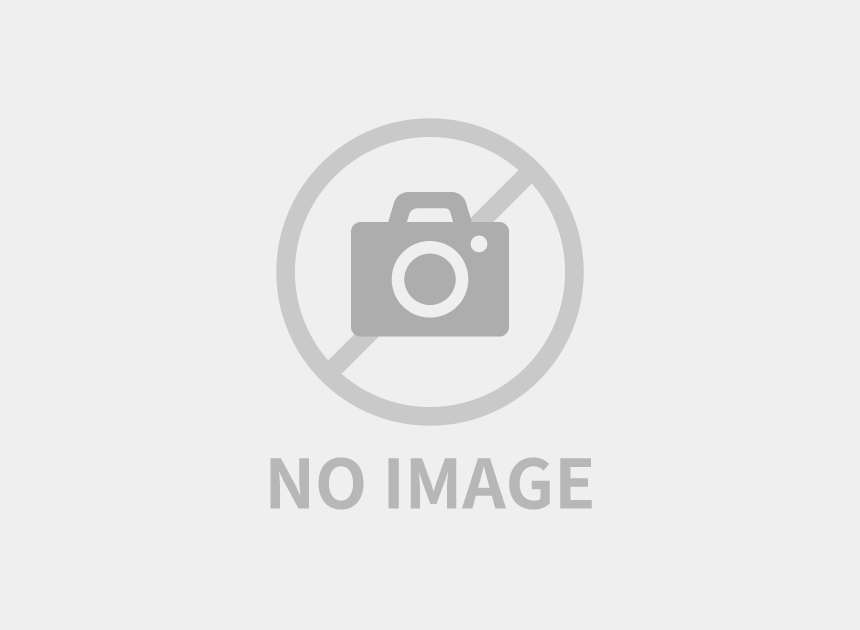
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第4号(令和7年7月号)を掲載しました。
-
Google Classroomを活用した授業実践
- 公開日
- 2025/07/15
- 更新日
- 2025/07/15
ICT・情報モラル教育
南魚沼市国際科では英語によるコミュニケーションを通して、相手の思いを受け止めたり、自国の文化や伝統の良さに気づいたりできる『心豊かでたくましい児童生徒の育成』を目指しています。
先日、学習指導センターのGoogle Classroomに市内の小学生より動画が送られてきました。国際科6年生が単元のまとめとして自分の地域のおすすめを紹介する動画でした。子どもたちはどう表現すれば、相手が興味をもってくれる動画になるか個人練習や話し合いを重ねながら試行錯誤した結果、相手意識をもった魅力的な動画となっていました。パフォーマンス練習を行う際に、ICTを効果的に活用していたのも良かったようです。
現在、国際科では、地域の国際大学の生徒と実際にコミュニケーションを取ったり、メッセージや作品を送ったりする等の目標を設定して英語学習や国際理解活動に取り組んでいます。メッセージや作品のやりとりを行う際にもICTを活用した工夫された取組が行われています。
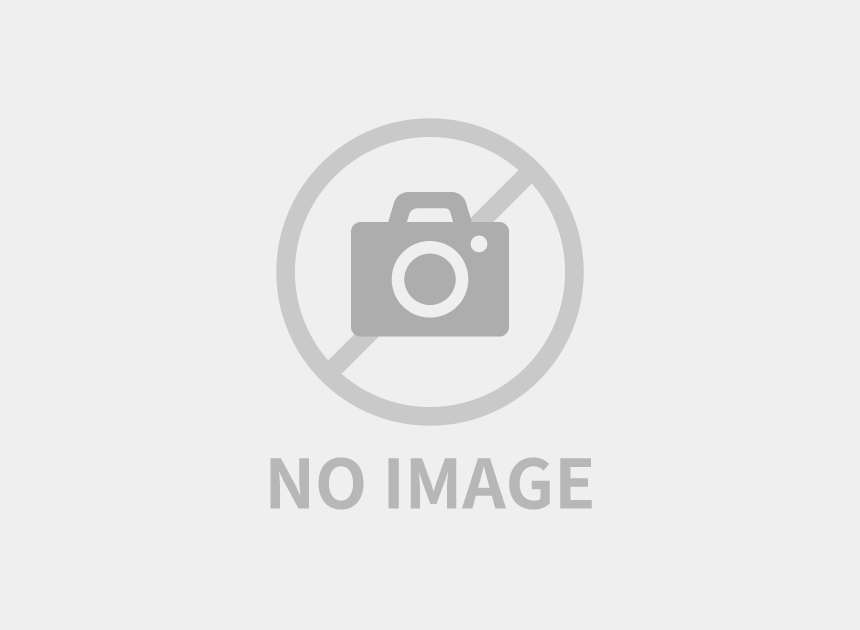
-
「読む力」育成に向けた授業づくり研修(社会科)が行われました(2025.7.8)
- 公開日
- 2025/07/09
- 更新日
- 2025/07/09
「読む力」の育成
南魚沼市学習指導センターでは、市内の学校の先生方と共に「読む力」育成のための取り組み方について研修を行っています。
7月8日(火)に六日町中学校で、授業づくり研修が行われました。
公開授業
授業は、2年生の社会科『日本の諸地域』中国・四国地方の学習でした。
課題は、「中国・四国地方における人口減少の現状と要因などを、様々な資料を組み合わせて説明すること」でした。
そのために、本時は、グループごとに異なる資料を読み、読み取ったことを交流する活動が行われました。
子供は話し合いながら、資料から分かることを書き出していきました(正しく読む)。
教師はグループを見て回り、必要に応じて「資料のタイトルの意味は?」「何が増えて、何が減っている?いつから変わっている?」などと、読む視点について助言しました。
グループの発表では、その都度教師は読み取られたことを評価し、事実の背景について補足しました。
その後は、発表内容を基に、各自が課題に対する考えをまとめることにしました(深く読む)。
どの子供も主体的・対話的に取り組んでいて、子供たちの❝社会科好き❞が感じられる授業でした。
研究協議
協議内容は「子供は資料を正しく読んでいたか」「子供の姿を支えた有効な手だては何であったか」「他にどのような手だてが必要か」でした。
先生方が授業で見取ったことを基に、議論が活発に行われ、次のことが共有されました。
資料を正しく読むために
・資料を読もうとする上で、子供が資料に興味をもつ必要がある。
・課題解決に必要な資料を選択判断することも、正しく読む力として大切である。
・ここで行うことは、資料に直接表されている「事実」を示すことであり、「推測」と分けなければならないことを理解する必要がある。
・資料を正しく読む上で、その資料から明らかにしようとすること(問い)をもつ必要がある。
さらに、資料を読む視点をもつ必要がある。
・他のグループの説明を理解する上で、「資料のどこを、どのように見ると、どういうことが分かるか」といった、各グループの思考のプロセスを共有する必要がある。
資料の読み方は正しいか、説明で不明な点はないか、子供が質疑応答するとよりよい。
・与えられた資料が課題に対しなぜ必要なのかについて見通しをもつ上で、課題を解決するために必要となる複数の小課題(問い)を最初に共有し、
すべての小課題に関わる資料を予めひととおり見ておくとよい。
その他
・グループで協力して活動を行う上で、日頃の学級指導や教科指導で、教師と子供たち、子供同士の信頼関係をつくっていくことが大切である。
-
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/06/19
- 更新日
- 2025/06/17
お知らせ
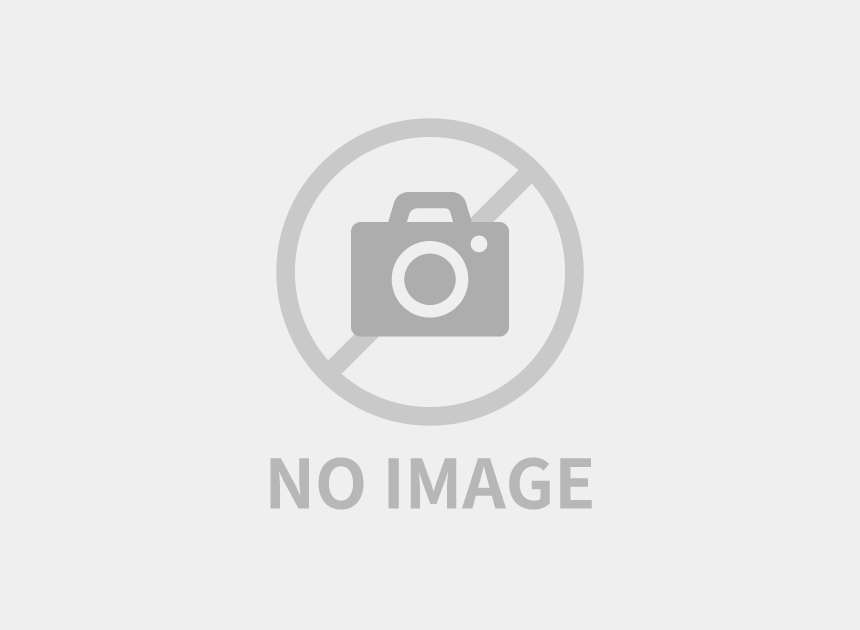
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第3号(令和7年6月号)を掲載しました。
-
センターだより掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/05/22
- 更新日
- 2025/05/22
お知らせ
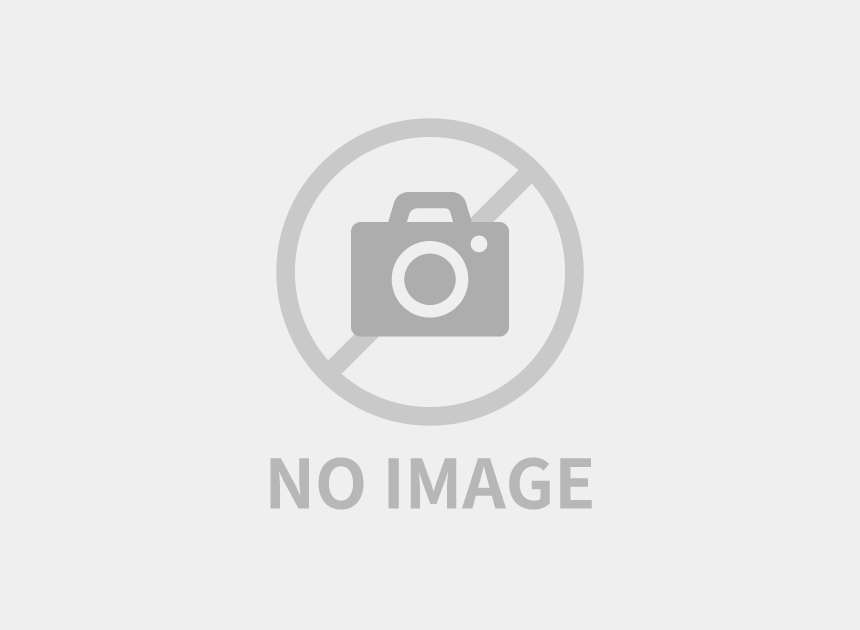
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第2号(令和7年5月号)を掲載しました。
-
「令和7年度 第1回 学力向上推進研修」が行われました(2025.5.13)
- 公開日
- 2025/05/19
- 更新日
- 2025/05/19
「読む力」の育成
5月13日(火)、令和7年度 第1回 学力向上推進研修がありました。学力向上のための取組を各学校で推進する研究主任と管理職が参加し、学習指導センターから事業説明を、学校間で情報交換を行いました。参加者の高い関心と前向きな気持ちが感じられる会になりました。
開会のあいさつ
岡村教育長が、学校現場で教育活動に尽力いただいている先生方へ感謝と激励を伝えた後、南魚沼市が「読む力」育成に重点を置くに至った経緯を話しました。そして、「『読む力』は、『学力向上』のためだけでなく、仕事や生活をしていく上で『生涯にわたり必要な力』であるため、義務教育段階で指導することは意義深い」といったお話がありました。
学習指導センターの説明
学習指導センター指導主事が、「読む力」育成についての南魚沼市の考え、「読む力」を育むための取組例、本年度の事業計画を説明しました。RST(リーディングスキルテスト)が対象としている「正しく読む力」を解説し、実証研究校(北辰小・六日町小中)の各教科の授業における効果的な取組や校内研修の進め方を例示しました。
各学校の情報交換
最後に、参加者で小グループを作り情報を交換しました。「『読む力』を育む学校の本年度の取組」をテーマに行いました。
紹介された取組
・音読などを大切にする。(例えば、朝、視写・聴写・音読をモジュールで取り組む。)
・共書き(内容を読みあげ黒板とノートに共に書くこと)を全学年・全学級で継続する。
・3年生以上は、そばに辞典をおき、ことばを調べさせる。意味を考えて理解できるようにする。
・読書:委員会の児童が20分休みに本の貸し出しをする。本の表紙の裏に子どもが昨年度書いた紹介文を添付してある。読書旬間を設定し地域の方が読み聞かせをする。司書が放送で本の紹介・読み聞かせをする。学校図書館はもちろん、市立図書館を有効活用する。
・教科ごとに「正しく読む力」「深く読む力」の具体を示して実践する。
・事前に教科書を読み込む。
・RSTから課題を捉え授業に生かす。 など
参加者の声
・「読む力」の育成に取り組む南魚沼市の考え方がよく分かった。
・他校の取組について知ることができ、とても良い研修となった。
・学んだことを自校職員に還元し、全校体制で読む力の育成に努めていきたい。 など
-
センターだより・文献目録掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/04/24
- 更新日
- 2025/04/23
お知らせ
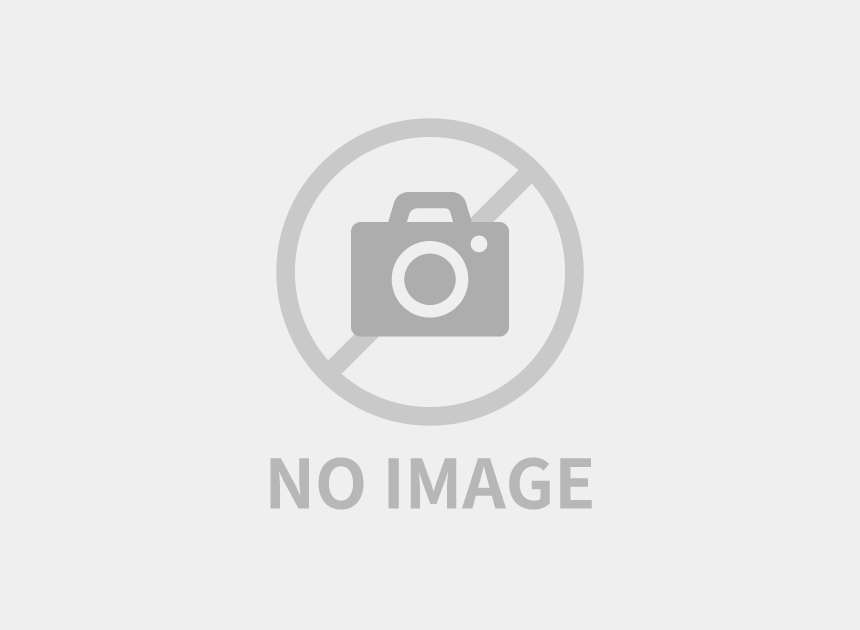
配布文書のページにセンターだよりと理センだよりの第1号(令和7年4月号)を掲載しました。また、文献目録令和6年度追加分も掲載しました。
-
研修講座掲載のお知らせ
- 公開日
- 2025/04/18
- 更新日
- 2025/04/18
お知らせ
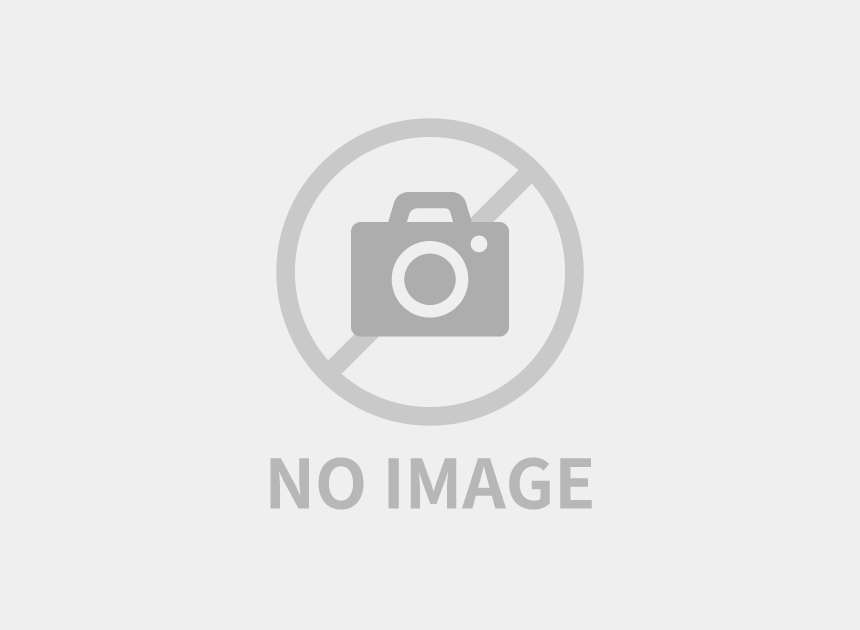
研修講座カレンダーのページに令和7年度の研修講座を掲載しました。一覧表は配布文書に令和7年度 研修講座一覧を掲載中です。
-
「令和6年度 第2回 学力向上推進研修」(2025.2.6)
- 公開日
- 2025/02/06
- 更新日
- 2025/02/06
「読む力」の育成
南魚沼市が学力向上に向けて「読む力」を育む取組を始めて約2年間が経ちました。実証研究校から、教師の見取りや子供の自己評価、RSTなどに基づいて実践報告がされました。参加者の意見や情報の交換も活発に行われ、充実した会となりました。
2月4日(火)、令和6年度 第2回 学力向上推進研修が行われました。各学校の研究主任が参加しました。始めに、岡村センター長(教育長)からビデオメッセージとして、「『読む力』は、学力向上のためだけでなく、生涯仕事や生活をしていく上で必要な力であるため、義務教育段階で指導することは意義深い」といったお話がありました。
続いて、実証研究校3校による実践発表を聞きました。
北辰小学校からは、様々な教科で「読む力」を意識した指導案作りと授業公開が増えたこと、「視写」「音読」「共書き」「線引き」など「正しく読む」ための取組が浸透してきたことなどが報告されました。
六日町小学校からは、各学年・学級の取組を通して、子供は分からない言葉を進んで質問したり辞書で調べたりするようになったこと、問題や文章をよく読み課題解決に向けてあきらめずに取り組むようになってきたことなどが報告されました。
六日町中学校からは、各教科のNRTの結果分析が「読む力」と関連付けて行われるようになったこと、NRT及びRSTの分析結果に基づいて、各教科で取組を工夫するようになってきたことなどが報告されました。
最後に、学習指導センターが「これまでの取組や研修等から見えてきたこと」と「次年度の取組の方向性」についてお話しました。
これまでの取組や研修等から見えてきたこと
・「読む力」は、書く力・話す力・聞く力などと関連して育まれる。
・「読む力」は、「文を読む力」だけではない。
・どの教科の学習にも、「正しく読む」場面と「深く読む」場面がある。
・「読む力」には、「様々な教科に共通するもの」がある。
・各教科の知識は、「読む力」とともに育まれる。
・「読む力」を育むための取組には、様々なものがある。
・RSTは、実態把握に必要な客観的資料である。
次年度の取組の方向性
・RSTで自校の実態把握。
・「読む力」を育む取組を入れた授業実践。
・ロイロノートやオクリンクを活用した深く読むための共有・交流。
・各教科の知識・技能の定着を図るための家庭学習の充実。
今回の研修が大変充実したものになったのは、実証研究校をはじめ、各校が「読む力」を育むためにいろいろと取り組んでいただいたおかげです。ありがとうございました。
今後もご協力をお願いします。
+1
-
情報モラル教育からデジタル・シティズンシップ教育へ ~2024.11.29 県生涯学習推進センターの研修より~
- 公開日
- 2024/12/03
- 更新日
- 2024/12/06
ICT・情報モラル教育
11月29日(金)、オンラインにて新潟県立生涯学習推進センター主催の「デジタル・シティズンシップ研修会」に、当センター指導主事が発表者として参加しました。これまでセンターで実施した2回の「情報モラル教育研修」の内容について発表しました。その後の研修では、講師の一般財団法人インターネット協会主任研究員である大久保真紀様から、「デジタル・シティズンシップ教育」「デジタルウェルビーイング」についてのお話しをお聞きしました。お話の内容を、キーワードと共に紹介します。
次々と生まれる新しいサービスや流行
note:文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォーム。大きな特徴は、自分の作ったマガジン(自分や他人の掲載されているトーク、テキスト、サウンド、イメージ、ムービーをまとめたもの)を「無料」もしくは「有料」で配信することができる。 BeReal:写真を共有するアプリで、アプリからの通知を受けてから2分以内に写真や動画を投稿する仕組み。「盛らないSNS」として人気。 ディスコ:動画を見ながらインスタントメッセージ(コミュニケーションサービス・チャットアプリ)・ビデオ通話・音声通話が可能なアプリであるDiscordの略。主にゲーム配信、ゲーム中のコミュニケーションで活用されている。 言葉の意味、わかりますか
グルーミング(チャイルドグルーミング):子どもからの信頼を得て、その罪悪感や羞恥心を利用する性的手なづけ。SNSで言葉巧みにわいせつ画像等を送らせるなど。 闇バイトに関する隠語・用語
・たたき:強盗や窃盗のこと。
・UD:受け子(U)と出し子(D)のこと。
・手押し:対面で直接薬物を売る、運ぶこと。
・野菜:大麻のこと。葉っぱ、草という言い方もある。他にもアイス(覚醒剤)、AK、×、罰(MDMA)などがある。
保護者が子どものスマホにこれら単語を見つけても、意味がわからなければ子どもは危険。
CEROのゲームレーティングマークや映画倫理機構(映倫)の区分
A(全年齢対象):マインクラフト、集まれどうぶつの森など
B(12才以上):スーパーマリオオデッセイ(マリオシリーズはほとんどがAでBは数本)など
C(15才以上):フォートナイト、モンスターハンターなど
D(17才以上):APEXなど
多くの小中学生がプレーしているフォートナイトやモンスターハンターは15才以上が対象のゲーム。映倫の区分も含め、親として注意を払う。
SNSの年齢制限(オーストラリアでの16歳未満禁止法)、女性教諭中傷動画投稿の疑いで中3と中1男子を逮捕(名誉毀損)、修学旅行で男子中学生が入浴中の女子生徒を盗撮し警察が捜査、と様々なネット関連のニュースが流れている。保護者が関心をもち、ある程度の知識を身に付けていなければ、子どもに話はできない。まずは「知ること」が大切。
お家の方の「責任」
ペアレンタルコントロール
・フィルタリングで有害情報等からの危機回避、年齢に応じたコンテンツでリテラシーを体得、使いすぎや依存の防止。
・端末は親の所有物、いつでも見る、いつでも取り上げると宣言しておく。
・ゲームや動画視聴以外にも、楽しいことがたくさんあることを子どもに認識させる(五感を使い、人と関わり、親子で体験する、楽しむ)。
保護者の「デジタル・シティズンシップ教育」
デジタルウェルビーイング(機器やテクノロジーを適切に使用して心身共に健康であること)を目指して。
・リアルでもネットでも、子どもには「命を大切にしてほしい」「節度をもって人と接してほしい」という親の願い。
・スマホ、ネットは「道具」。楽しい時間を過ごすため、生活を豊かにするため、自分の夢や願いをかなえるためという「目的」のために使うもの。
・物事もネットも表裏一体、光(利便性)もあれば闇(危険性)もある。ネットやゲーム、SNS自体が悪いのではない、そこに悪い人が紛れ込んでいる。
・「親が自分よりスマホを大事にしていると感じることがある」と回答した子どもが2割。子どもは親の映し鏡、まずは大人のスマホ利用を見直す。
学校ではよく、スマホ等の所持については「お家の判断で」と言います。だからといって、「デジタル・シティズンシップ教育」を行わなくてもよいとはなりません。学習指導要領では「情報モラル」を「情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度」と示しています。また、教育の情報化に関する手引では「他者への影響を考え、人権、知的財産等の自他の権利を尊重し、情報社会での行動に責任を持つことや、危機回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康とのかかわりを理解することなど」と示しています。内閣府からは、「次期指導要領では、デジタル・シティズンシップ教育を各教科で推進する」「ICT機器の具体的な操作に関しての心構えとして、端末を活用しながら身に付けていく」という声が聞かれます。
南魚沼市でもようやく教育活動におけるICT活用が浸透してきました。子どもたちが適切にICTを活用できるよう、今後は、端末を1つの筆記用具として、子ども自身が取捨選択しながら活用できる学習の構想、学校を離れても安全にネットを活用できる「心構え」を身に付ける教育が求められます。そのため、先生方にはまず「デジタル・シティズンシップ教育」に注目していただければと思います。
記事メニュー


